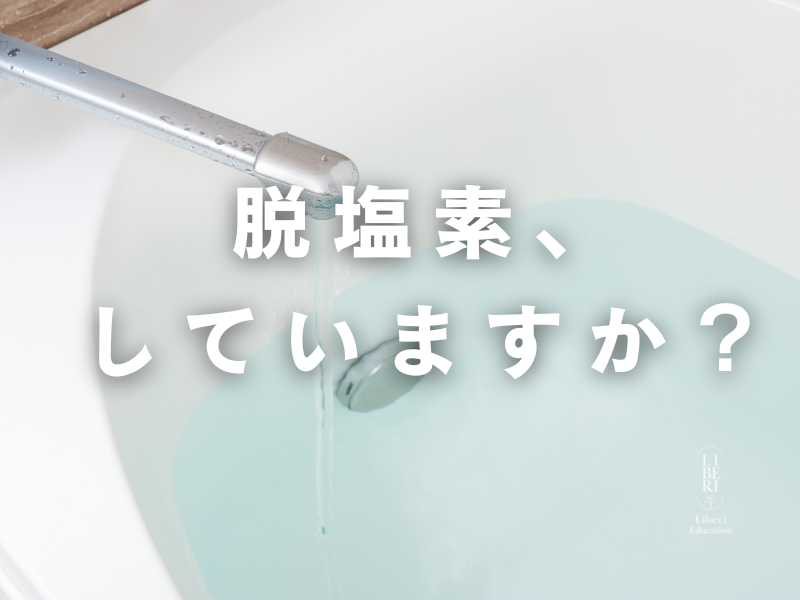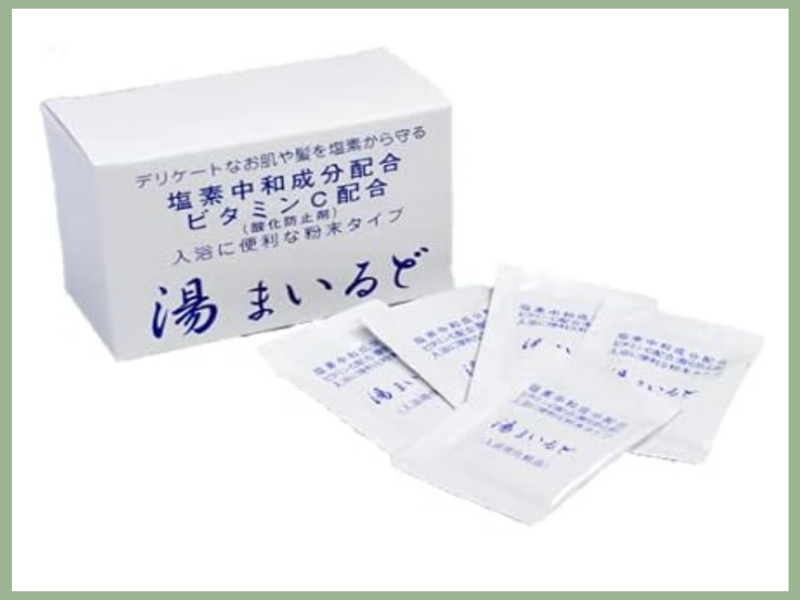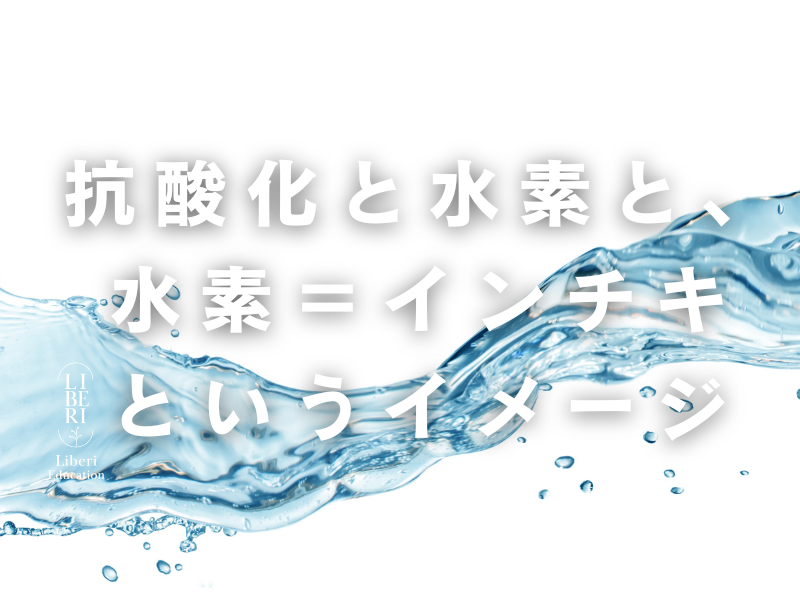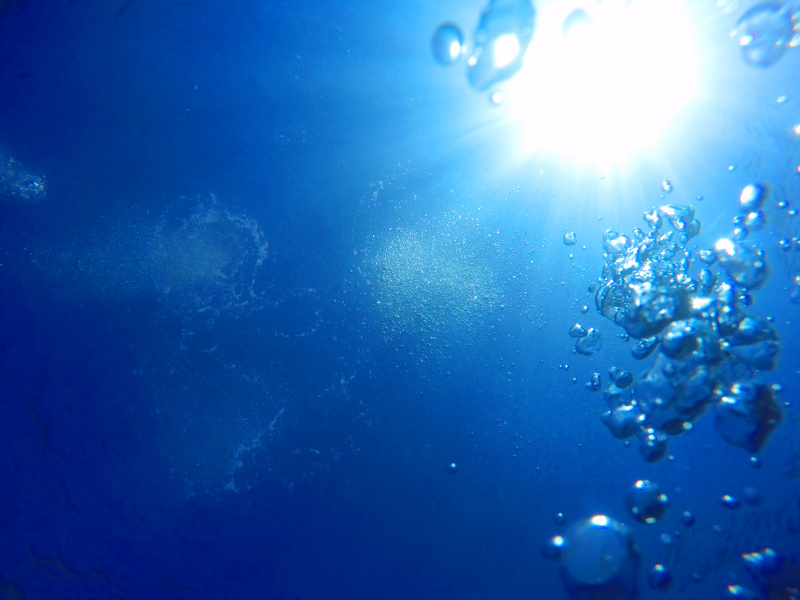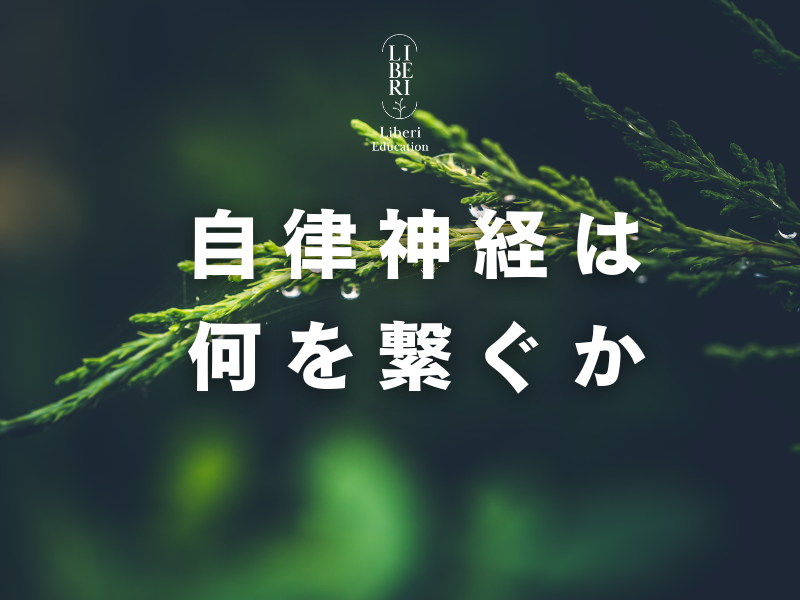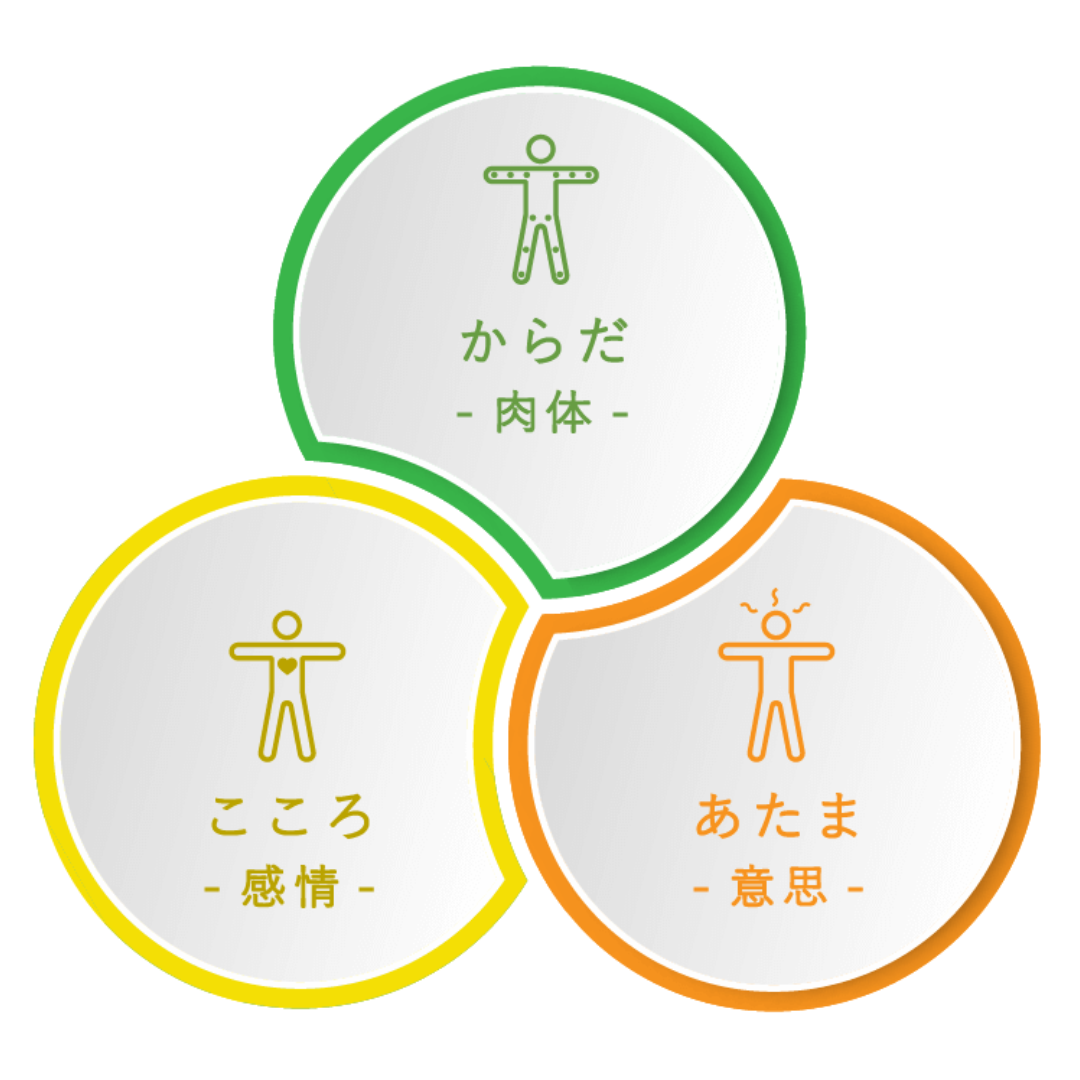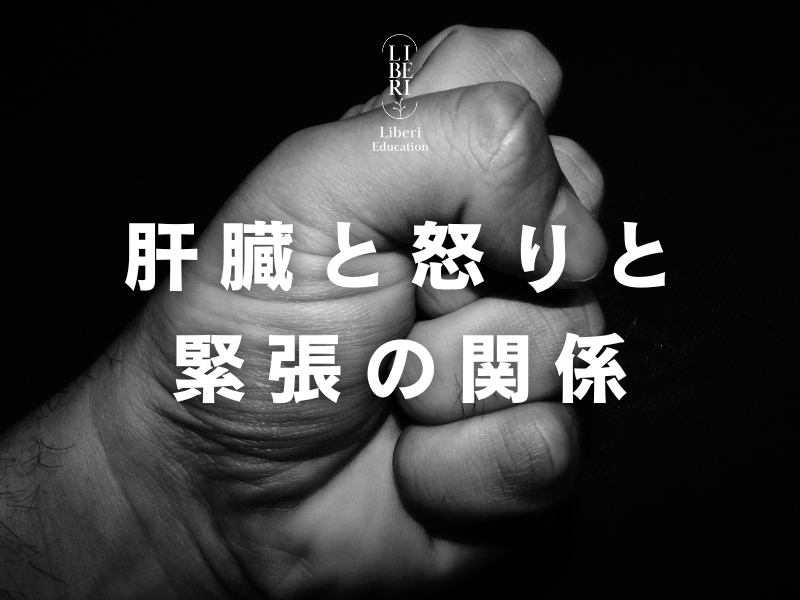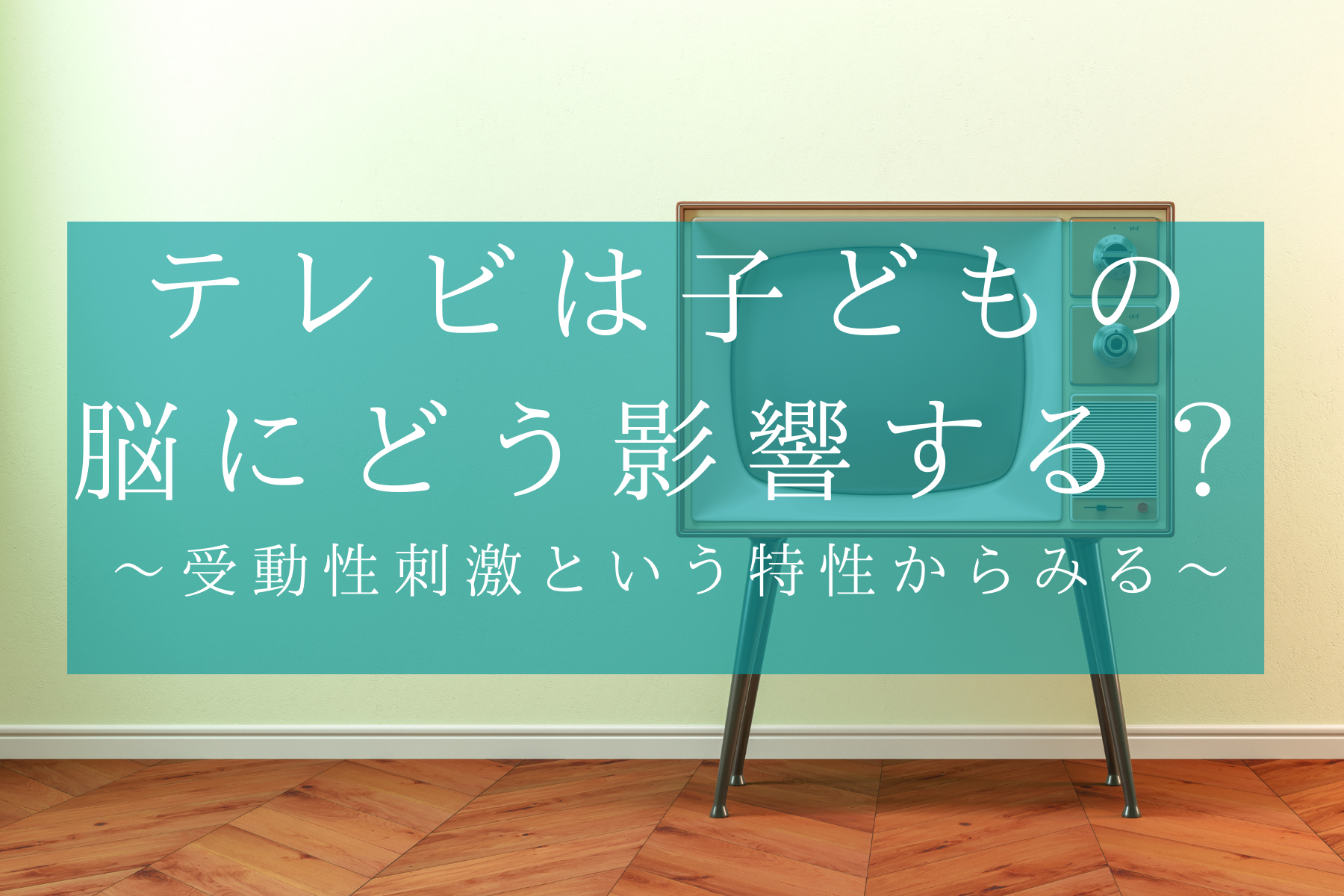暑すぎるからだにご注意
夏は少し暑い室内にいるとき、それから外から戻ってきたてのまだからだが暑い時、体内がなんとなくほかほかしていたり、心拍が高いような、そんな時はありませんか。そのような状態のままお食事をすると血糖値が跳ね上がることがあります。血糖値が跳ね上がりますと、「動悸・息切れ・頭のくらくら感・目のチカチカ・やる気のなさ」などが起きます。そしてその後は急激に血糖が下がりやすくなりますので「眠気・異様な飢餓感・甘いものへの渇望・カフェイン飲料への渇望・やる気のなさ・だるさ・夕方のしんどさ」などが起きやすくなります。

体温が高くなりすぎると(熱がこもると)、私たちの自律神経と脳は負荷がかかります。エンジンのオーバーヒートのようなものです。また熱(暑)すぎるとアドレナリンが分泌されます。さらに夏ですと、常に暑いですから、アドレナリンでの発汗なのか、汗なのかは分かりにくい。して、自分がアドレナリン分泌をしていることに気づきにくい。結果その状態のまま食事をして、血糖値がとても上がりやすくなります。
夏の外出時など、食事の後に異様にダルくなることありませんか?それが何度も続きますと、見事に夏バテと称される「副腎疲労」になりやすいのです。
涼しくなってきた9月くらいも、やはり注意が必要です。涼しくなってきたからと、エアコンをつけずに室内で過ごし、結果からだに熱がこもっており、血糖値が上がりやすいことがあります。

では、どうしたらいいのか。まず食事をする前にからだを冷やすことです。食事をするお部屋が心地よい涼しさであること。それから、冷水などを飲んで深部を冷やしていくことも大事です。からだを冷やさない、と常温水にこだわっていますと、実はからだがオーバーヒートを起こしていることもありますよ。
急に食べ始めるのではなく、涼み、冷たい水(お茶)をゆっくり飲んで、それからゆっくり食事をしてくださいね。血糖値の乱高下は、万病の元ですので、しっかり対策をしていきましょう〜!