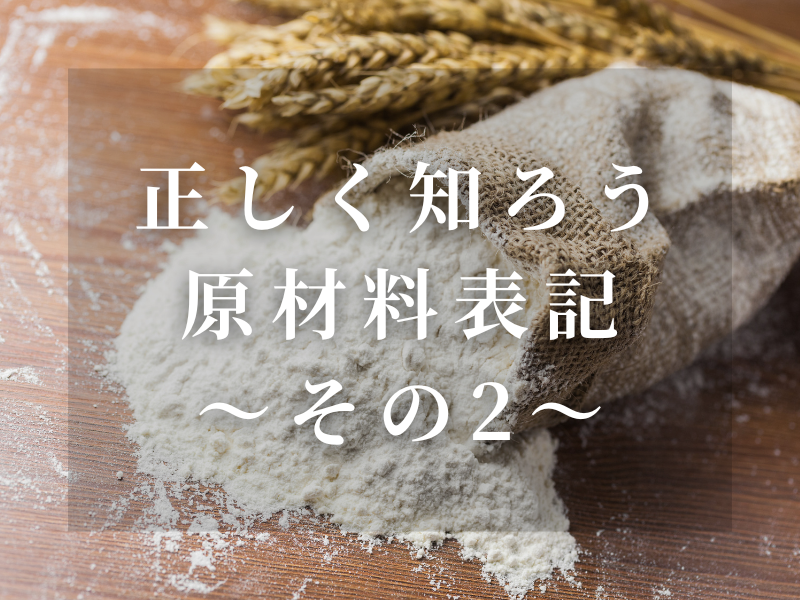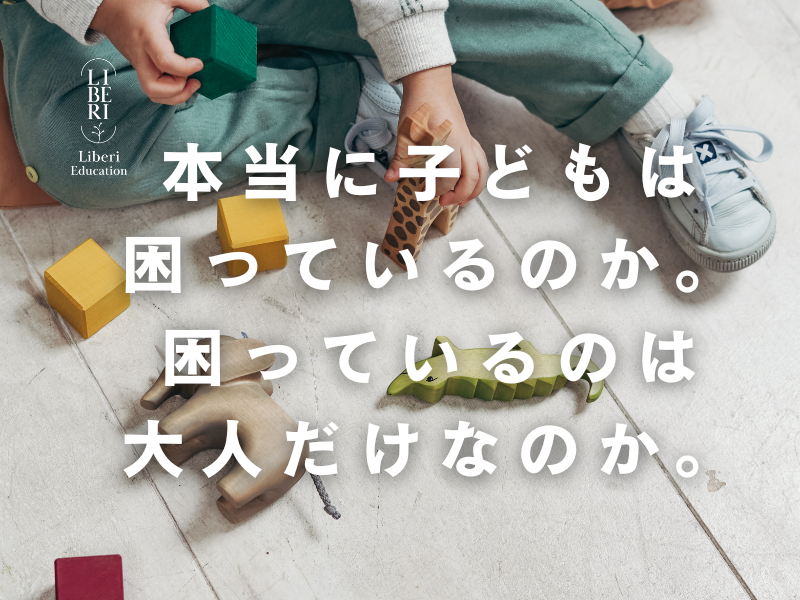遺伝子組み換え食品の影響
スーパーでお豆腐やお菓子を手に取ったとき、原材料に「遺伝子組み換えでない」と書かれた表示を見かけたことはありませんか?実は、この「遺伝子組み換え食品」というのは、作物が育つ過程において、害虫に強くしたり、除草剤をまいても枯れないようにしたりと、効率よく作物を育てられるよう工夫されて作られたものです。

こうした遺伝子組み換え食品には、健康への影響として「自然界に存在しない遺伝子を取り込んでいることによる長期的な影響がまだ十分に分かっていない」という不安があります。さらに、環境面でも「遺伝子組み換え作物が周囲の植物と交雑して自然の生態系に影響する可能性」や「除草剤の大量使用による土壌や環境への負担」といった点も指摘されています。
特に毎日の食卓に上がる大豆やとうもろこしは加工食品にも幅広く使われているため、知らないうちに遺伝子組み換え食品を口にしてしまう可能性もあります。日本で流通している遺伝子組み換え作物は、大豆、とうもろこし、じゃがいも、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からし菜などが代表的です。
だからこそ大切なのが、選ぶ時に「食品表示」をしっかり確認できることです。遺伝子組み換え食品の見分け方を確認していきましょう。
遺伝子組み換え食品の見分け方
日本の食品表示のルールとして、「主な原材料(上位3位以内)」で、かつ「全重量の5%以上を占める原材料」について、遺伝子組み換えの「大豆、とうもろこし、ばれいしょ、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からし菜」のいずれかを使っている(または混入している可能性がある)場合は、必ず「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分」などの表示をしなければならない義務があります。なので、もし上記の食品について、特に何の表示も無い場合、それは「遺伝子組み換えのものは使われていない」ということです。
一方で、原材料の大豆やじゃがいもの後、カッコ書きで(遺伝子組み換えでない)という表示を目にすることもありますよね。これは、購入する人がが安心して選べるよう配慮して、メーカーが任意で表示してくれているものです。
しかし最近、この「遺伝子組み換えでない」の表示された商品は、少しずつ減ってきています。実は、2023年に食品表示の基準が、厳しく改定されたためです。

それまでは「遺伝子組み換え食品が意図せず混入してしまった場合も、全体の5%以下なら【遺伝子組み換えでない】と表記できる」というルールでした。この【意図せず混入する】というのは、例えば、トウモロコシや大豆などの収穫の時、コンテナ等に残った遺伝子組み換えのものが、少量混入してしまうことを言います。ジャガイモのような大きさの作物なら、まず混ざる心配はありませんが、豆など細かい収穫物では、混入を完璧に避けることは難しいのです。
2023年の改定後は「遺伝子組み換え食品が不検出(100%混ざっていない)の場合に限り表記できる」ルールになったため、「遺伝子組み換えでない」と表示できる商品がほとんどなくなったのです(一部のジャガイモくらい)。ただし、従来と同じ基準の「意図しない混入が5%未満」の場合は、「大豆(分別生産流通管理済み)」や「大豆(遺伝子組み換え混入防止管理済)」のように表示することが許可されているので、代わりにメーカーの任意でこの表示がされている商品は増えています。特に、お豆腐の原材料表示の大豆でよく見られるようになりました。

ただし、遺伝子組み換え食品の表示ルールには例外があります。植物油や醤油は、遺伝子組み換え作物を原料に使っても表示の義務がありません。これは、最新の技術で成分を調べても、遺伝子組み換えの痕跡が見つからないためです。
また、原材料に表示されている調味料や甘味料に遺伝子組み換え食品が使われている場合も、キャリーオーバー(原料由来の成分の影響)のため、最終商品への表示義務はありません。そのため、表示だけを見て安心せず、「異性化液糖が使われているなら、遺伝子組み換えのトウモロコシが使われているかも」といったように、細かい部分も見ていくのがおすすめです。
表示に気づけると、買い物がちょっと楽しくなりますよ。次にスーパーへ行ったときにぜひ注目してみてくださいね。